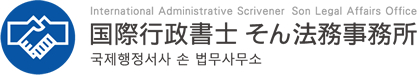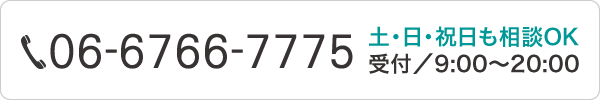相続・遺言書作成

相続とは、人が亡くなった場合にその人が所有していた財産上の権利・義務を子や配偶者など親族が引き継ぐことを言います。
亡くなった人のことを「被相続人」と言い、その一方その人の財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。
日本では、民法の中に相続についての規定を置き、相続人の範囲や相続の方法、遺言の方式や遺留分について知ることができます。
普通の人が一生の中で相続を経験することはほんの数回でしょう。
しかし、そのわずか数回の出来事が、自身のその後の人生や周囲の人たちとの人間関係をぶち壊す恐れのあるとても大切でとても怖い出来事にもなりえます。
それを防ぐためにも、相続についてのルールを知り、家族が「お金」の行方に振り回されてバラバラにならないようにすることが重要です。
相続業務
相続業務
相続の準拠法
準拠法とは、ある事象に適用される法律のことを言い、人が亡くなって開始される相続の場合は被相続人の本国法がその相続に適用される準拠法となります。
すなわち、日本人がどこの国で亡くなろうが、日本国籍を有する限り日本の民法で相続が開始され、反対に日本にいる外国人の場合はその方が日本生まれの日本育ちであろうが基本的にはその方の国籍国の法律が適用されます。
日本には多くの外国人が住んでいますが、特に多い在日韓国・朝鮮人について考えると、韓国籍の方が亡くなると日本の「通則法」と韓国の国際私法により、韓国の民法が準拠法となります。
朝鮮籍の方の場合は、日本法・朝鮮法により日本の民法での相続が可能となります。
遺産分割
相続人間で遺産を分け合う話し合いのことを遺産分割協議と言います。
たいていの方が遺言をせずに亡くなられる場合が多いかと思いますが、死人に口なしと言うように、亡くなった方の意思を相続に反映させることはほとんどの場合できません。
ではどのように相続財産を分配するのかというと、一つは法定相続分と言って法により定められた割合で相続人間で遺産を分け合います。
ある意味公平にも感じられますが、家族間でも亡くなられた方への貢献度や生前の親密度、亡くなられる前に受けた恩恵など様々です。
日本の民法では相続人同士で生前の出来事なども加味して遺産を分け合うことを認めていて、その話し合いのことを遺産分割協議と言います。
当然ですが、遺産分割協議に参加できるのは相続人に限られていて、赤の他人がこれに関与することはできません。
法定相続人
遺産を相続する人のことを相続人と呼びますが、ではいったい誰が相続人になるのか?
その問題を解決してくれるのも民法に答えがあります。
民法第5編「相続」の部分に誰が相続するのかについての規定があります。日本では、第一順位の相続人として子、第二順位が直系尊属(父母や祖父母)で、第三順位が兄弟姉妹です。
これは、前の順位者がいない場合に初めて後の順位者の出番が回ってくように理解してください。
また、配偶者(妻や夫)は常に相続人となり、その取り分も他の相続人を上回るような規定となっています。
高齢者と結婚した若者が遺産目当てと言われるのは、この民法の規定によるところが大きいのです。
実際、30年間連れ添った内縁関係のパートナーと婚姻期間1年の配偶者とを比較した場合、前者の取り分がゼロであるのに対し、後者は少なくとも遺産の1/4(遺留分)を確実に手にすることができます。
遺言業務
遺言業務
日本の遺言に関する法律

民法961条
「満15歳以上の者は遺言をすることができる。」
民法964条
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」
遺言は、亡くなられた方がこの世で最後に行なえる意思表示です。
それまで自分が築いた財産(お金や不動産、アイデアや技術など)を自分の死後、誰にどのように分け与えるのかを自分の意思で決められます。
当然のことと感じられましょうが、ほとんどの人がそれを為せずに死んでいきます。死は誰にも予測できません。遺言をすることは、残された家族へ最後のメッセージを残す行為であり、世の中へ向けた最後の自己表現でもあるのです。
亡くなった方がどのように考えどんな思いで死んでいったのか、遺言を受け取れずに残された家族は知る術が無いのです。967条では、「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。」と定めており、より確実性の高い公証人を介しての遺言方式も選択可能です。