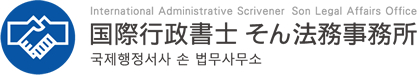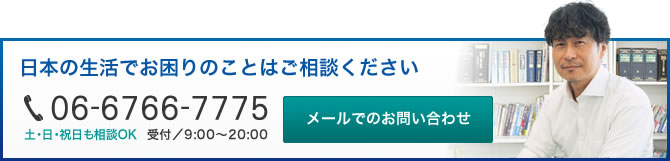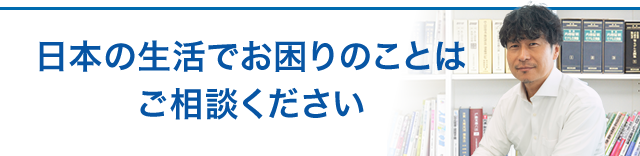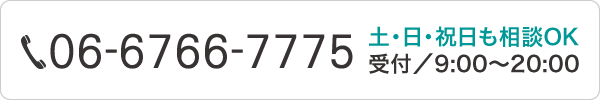在留特別許可一覧
不法就労助長の罪。
- 2012.04.25(水)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。
何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。
入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。
幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。
その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。
外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)
また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。
それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。
不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。
以下、参考条文。
入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
世界は言葉でできている。
- 2011.10.14(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 憤慨 , 日本語
昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。
過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。
私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。
日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。
私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。
私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)
それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。
これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。
何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。
世界は言葉でできているのだから、、、、
?
在留特別許可。
入管法54条の「法務大臣の裁決の特例」では、以下の様に定めている。(注:条文抜粋です) 法務大臣は、容疑者(オーバーステイ等)が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
この条文の存在により、多くの不法滞在外国人が日本で正規在留者として復活を果たすことが出来たことだろう。
私も、「止むを得ない事情により日本を離れることが出来ずに不法在留をすることとなった」外国人家族や外国人配偶者を沢山見てきた。
業務として、彼らが行う行政や入管への手続をお手伝いしたこともある。
現在では、入管側でも慎重に調査をして厳格な判断を下しているようで、いわゆる「審査期間」は短くて1年、長いケースだと2年を要することもあるようだ。
その間、不法滞在者は国民健康保険へ加入出来ず、また、特別な場合を除いて就労活動も認められない。
何より、日本からの出国が制限されるため、在留特別許可、すなわち日本人配偶者や永住者との日本での結婚生活の継続を取るか、それとも本国の親の死に目に立ち会うことを取るか、の選択を迫られることもある。
こんな究極の選択を、長い歴史を積み重ねて自分達のより良い暮らしを求め続けてきた人間が、同じ人間に課している光景を見るたび、人間の無能さを痛感せざるを得ない。
今日、うれしい連絡が来た。
上で述べた「在留特別許可」により、日本での正規滞在者としての復活を果たした女性からだ。
彼女には、是非とも日本で幸せな暮らしを送っていただきたい。
何よりも、この間(彼女の場合、審査(調査)に2年の時間を費やした)会えなかった本国の家族に、早く会いに行って欲しい。
仮放免を許可された不法滞在者の生活保護受給について。
『外国人は生活保護法第1条及び第2条により法の適用対象とならず、法による保護は受けられないが、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知により、当分の間法による保護に準ずる取扱いをすることとされている。』
上記は役所から入手した生活保護についての問答集の一部です。
また、上記にある『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』の『昭和57年1月4日社保第1号による改正』なる文書では、以下のような問答事例が存在する。
問:無登録の外国人が仮放免された場合には、外国人登録書を所持していなくても、保護して差し支えないか。
答:無登録の外国人が出入国管理及び難民認定法第52条第6項の規定により放免され、又は同法54条第2項の規定により仮放免される場合には、それぞれ所定の許可書が交付され、その交付にあたりただちに居住地の市区町村長に対し外国人登録の申請をすべきむねの注意が与えられるから、登録の申請をしていない者が保護の申請をした場合には、まず登録の手続を行ったうえ有効な登録証明書の交付を受けてこれを呈示するよう指導すること。ただし登録の申請をしたが未だ登録証明書の交付を受けていない者については、外国人登録証明書交付予定期間指定書の呈示を求め、所定の手続により<strong>保護を実施して差し支えない</strong>こと。この場合、放免又は仮放免中の居住地は指定されているものであるから、この点について前記許可書の呈示を求めて確認すること。なお、刑の執行を停止された者、仮出獄を許された者等が無登録である場合の取扱いも右同様であること。
前にご紹介した『中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪事件』のある段階においては、大阪市健康福祉局から厚生労働省社会・援護局保護課への照会の際に上記の『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』についての記述があります。
ここに挙げた『問答』の厳格な適用を望む。
日本に滞在するメリットとは?
4月5日付、法務省入国管理局の発表によると、平成23年1月1日時点での不法残留者数は7万8488人とのことだ。
平成16年には22万人近くいたはずの不法残留者が3分の1に減少したのだ。
入国管理局の必死の取締りの成果だと思う。
実際、この1、2年はいわゆる在留特別許可事案の依頼がめっきり減ってしまった。
長期間の日本での不法在留状態から抜け出すべく、日本人や永住者の配偶者を伴って相談に来る方たちも、本当に少なくなった。 私の経験上、不法在留(オーバーステイ)をして得をしている外国人をあまり目にしたことが無い。
ほとんどの方たちは毎日を怯えながら過ごし、職場でも不法就労外国人として劣悪な環境での労働を余儀なくされていた。 中には仕事場で怪我をしても病院へ行けず、使い物にならなくなったと見るや突然解雇されてしまった人もいた。
ちなみに、現状ではオーバーステイの外国人でも労災保険の適用はあり、労働基準監督署は割と見方についてくれる。 とにかく日本にいても苦労ばかりしている不法滞在者が多く、その人たちに「日本に滞在するメリット」を聞いても、ほとんどの人は答えを持っていないのだ。
入管の摘発によって退去強制される外国人の中には、案外「日本とおさらばするケジメがついた」と胸をなでおろしている人が多くいたりもするかも。
※参考(不法残留者数に関するデータ) http://www.moj.go.jp/content/000072624.pdf